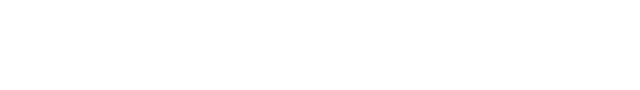加齢黄斑変性
加齢黄斑変性とは
加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)とは、網膜の中心部である黄斑に異常が生じる疾患です。新生血管型と萎縮型の2つの病型があります。加齢黄斑変性のリスクになるのは、加齢、喫煙、肥満、日光への曝露などです。
新生血管型
新生血管型の加齢黄斑変性は、網膜に生じた異常な血管(新生血管)から血液や水分が漏出することで、網膜内や網膜下に出血や浮腫が生じます。新生血管はVEGF(血管内皮細胞増殖因子)によって誘導されるので、抗VEGF薬の硝子体内注射を行うことで新生血管の勢いを抑制します。症状の進行が速く一度障害された網膜の機能は元通りに戻ることはないため、早期の診断と治療が重要です。
萎縮型
萎縮型の加齢黄斑変性は、加齢と共に黄斑部の網膜の萎縮が進行し、進行すると境界明瞭な黄斑部の萎縮にいたります(地図状萎縮と呼ばれます)。
症状の進行は緩徐ですが、有効な治療法がありません。
加齢黄斑変性の症状
早期の加齢黄斑変性では見え方の変化はわずかであるため、自覚症状がないこともあります。病気が進行すると視力の低下に加えて、物がゆがんで見える、中心部が見えにくいなどの症状を生じます。
下記の格子状の表を用いると、日常生活では自覚することができない早期の加齢黄斑変性を発見することができます。格子状の表を見た時に格子のゆがみや一部が黒く見えるような場合には、眼科での精査が必要です。
物がゆがんで見える病気には、加齢黄斑変性以外にも黄斑前膜、黄斑円孔、糖尿病黄斑浮腫などがあります。
加齢黄斑変性の診断
眼底写真、OCT(網膜の断面をみる検査)、蛍光眼底造影検査などを用いて診断を行います。
新生血管型加齢黄斑変性は、新生血管の存在する位置により病型が分けられます。脈絡膜由来の新生血管が網膜色素上皮の下に限局する場合を1型MNV(macular neovascularization)、網膜色素上皮を超えて網膜下へ伸展したものを2型MNVといいます。また、網膜血管由来の新生血管であるものは3型MNVに分類されます。
上記の眼底写真では、黄斑部に網膜出血を認めます。OCTでは、新生血管に加えて、網膜内の出血や浮腫を認めます。
加齢黄斑変性の治療
抗VEGF薬の硝子体内注射
加齢黄斑変性の原因である新生血管はVEGF(血管内皮細胞増殖因子)によって誘導されます。このVEGFの作用を抑えるために、抗VEGF薬を眼内に注射(硝子体内注射)を行います。加齢黄斑変性に対して、まず最初に行う治療法です。
治療開始時は、1ヶ月の間隔を空けて合計3回の注射を行います(導入期の治療)。その後は定期的の病状の経過をみながら、1〜3ヶ月毎に追加の注射を行います(維持期の治療)。多くの場合には長期間に渡る繰り返しの注射が必要になります。硝子体内注射の詳細は別ページで紹介しています。
光線力学療法(PDT)
抗VEGF薬硝子体内注射だけでは治療が困難な難治性の加齢黄斑変性に対して行う治療法で、特殊なレーザーを用いた治療です。当院では光線力学療法には対応していないため、治療が必要な場合には専門の医療機関へご紹介させていただきます。
加齢黄斑変性の治療費用
抗VEGF薬の硝子体内注射はは保険適用になるため、患者様の年齢や収入によって費用の負担が変わります。使用する薬剤によっても費用は異なり、費用の概算は下記のとおりです。
医療費が高額になる場合に、高額療養費制度の利用により窓口での支払い額を軽減できることがあります。詳しくは『高額療養費制度』をご覧ください。
加齢黄斑変性の前段階
ドルーゼンとは
加齢黄斑変性症の前段階の病変にはドルーゼンと呼ばれるものがあり、眼底に黄白色の沈着物として認められます。
ドルーゼンは長年にわたってほとんど変化しないこともありますが、ドルーゼンの数や大きさが増加する傾向にある場合には、加齢黄斑変性に移行するリスクが高いため定期的な検査が必要になります。特に片方の眼に加齢黄斑変性を発症した場合には、もう片方の眼も加齢黄斑変性になる確率が高まります。
加齢黄斑変性の予防
加齢黄斑変性を発症した場合には抗VEGF薬硝子体内注射による治療を行いますが、加齢黄斑変性の発症を予防する方法もあります。
AREDS2という大規模臨床研究において、禁煙とライフスタイルの改善に加えて、ルテインを含有するサプリメントを摂取することが加齢黄斑変性の発症予防に有効であることが示されました。サプリメントは「ビタミンC、ビタミンE、ルテイン、ゼアキサンチン、亜鉛、銅」を含むものとされており、これらを含むサプリメントが各社から販売されています。製品の一例として、参天製薬の「サンテルタックス®︎20V」があります。
よくある質問
注射はいつまで続きますか?
多くの場合で抗VEGF薬の硝子体内注射は長年に渡り繰り返し必要になります。まれに病状が落ち着き注射が不要になることがありますが、事前に予想することはできません。
禁煙した方がいいですか?
非喫煙者と比較して、喫煙習慣がある方の加齢黄斑変性の発症リスクは2-4倍になると報告されています。加齢黄斑変性の発症を予防するために禁煙することは重要です。
記事監修者について

日本眼科学会認定 眼科専門医
東京科学大学眼科 非常勤講師
大学病院や基幹病院において多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京科学大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。