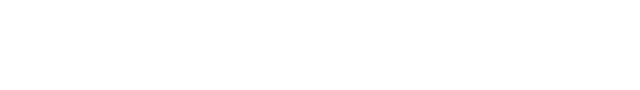黄斑前膜(網膜前膜)
黄斑前膜とは
黄斑前膜(おうはんぜんまく)は網膜の中心部(黄斑)の前に、異常な膜が形成される病気です。網膜前膜、黄斑上膜、網膜上膜、セロファン網膜症、黄斑パッカーなどと呼ばれることもあります。40歳以上のおよそ20人に1人が黄斑前膜を発症すると言われており、健康診断や人間ドックなどで指摘されることが多い疾患です。黄斑前膜が網膜を牽引することで網膜の形が変化し、視力低下やゆがんで見える(変視症)などの症状を生じます。
多くの場合には経過をみることが可能ですが、程度によっては手術(硝子体手術)が必要になるため、以前に黄斑前膜(黄斑上膜、網膜前膜、網膜上膜)を指摘されたことがある方は、硝子体手術に対応している眼科で一度診察を受けておくことが大切です。
黄斑前膜の症状
黄斑前膜により、黄斑の中心部(中心窩:ちゅうしんか)の構造が歪んでくると、視力低下、歪んでみえる症状(変視症)、物の大きさが変わって見えるなどの症状が出現します。初期段階では日常生活で症状を自覚することは少なく、アムスラーチャートと呼ばれる格子状の表で症状を確認することができます。
歪んで見える症状は一度出現すると、手術により黄斑前膜を除去できても完全に症状がなくなることはほとんどありません。視力が比較的良好であっても、変視症が出ている場合には手術を検討した方がよい場合があります。
変視症を生じる疾患
黄斑前膜以外に変視症を生じる疾患としては、黄斑円孔、加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症などの疾患があります。いずれの場合にも、手術や抗VEGF薬の硝子体内注射などが必要になるため、自覚症状がある場合には眼科を受診する必要があります。
黄斑前膜の診断
黄斑前膜の診断は、眼底検査(眼底写真)、網膜の断面図をみるOCT検査によって行います。
眼底検査では、橙色の眼底に白色の反射を伴う膜状の組織を認めます。黄斑前膜が網膜を牽引する力が強い場合には、網膜に皺がよっている所見も観察することができます。
OCT検査では、正常な網膜の上に異常な膜である黄斑前膜が存在するのがわかります。また、黄斑前膜によって牽引された網膜の層構造が、どの程度乱れているのかを確認するのにも有用です。
黄斑前膜の症例写真
症例1:進行した黄斑前膜
黄斑前膜(黄色矢印)によって網膜が著しく変形した状態です。網膜が全体的に肥厚し、正常構造でみられる中心部の凹みも完全に消失しています。ここまで進行した場合には、手術によって黄斑前膜を除去することができても、視力の回復は限定的となってしまいます。
症例2:分層円孔を伴う黄斑前膜
網膜の上に形成された黄斑前膜(黄色矢印)が網膜を牽引することにより、網膜の層構造はさまざまに変形します。特に赤矢印の部分では、網膜の中心部分に穴があく分層円孔という状態を生じています。
症例3:黄斑パッカー
網膜裂孔や網膜剥離に続発した黄斑前膜を黄斑パッカーといいます。網膜剥離は網膜に穴があくことが原因で発症しますが、この網膜に穴があいた時に眼内に網膜色素上皮細胞が散布され、この細胞が黄斑部の網膜に付着し、細胞が増殖することで黄斑パッカーが形成されます。黄斑パッカーは通常の黄斑前膜と比べて、急速に進行し視力障害も強いことが多いとされています。
下の写真は、網膜剥離に対して硝子体手術をおこなった約1か月後の網膜は正常範囲内でしたが、約2か月後には黄斑パッカーが出現し、著しく網膜の形がゆがめられています。
黄斑前膜の治療方針
初期の黄斑前膜
黄斑前膜が存在していても、網膜の形態がほとんど変化していない場合や、黄斑の中心部(中心窩)の構造が保たれている場合には、治療をせずに様子をみることができます。また、網膜の構造に少し変化を生じていても、視力低下や変視症がなければ経過観察を行うことが可能です。いずれにせよ、黄斑前膜が自然に治癒することはないため、定期的な経過観察を行うことが大切です。
進行した黄斑前膜
黄斑前膜により網膜の構造が障害され、視力低下や変視症を生じるようになると、治療を行っても見え方の改善は限定的になります。変視症などの視機能の低下を最小限に抑えるために、定期的な経過観察を行う中で、適切な時期に手術を行うことが重要です。
黄斑前膜の手術
硝子体手術
黄斑前膜の治療は硝子体手術で、眼内の硝子体と黄斑前膜を除去するというものです。当院は日帰り硝子体手術を行っているため、日帰りで治療可能です。白内障手術が済んでいない場合には、硝子体手術の際に白内障も同時に治療することが多く、硝子体手術と白内障手術を同時に行った場合の所要時間は合計で15分程度です。
術中写真(黄斑前膜を除去)
左側の写真は、黄斑前膜が白色に染められたところです。右側の写真では、鑷子(せっし)を用いて黄斑前膜を把持しながら剥いている場面で、黄斑前膜が除去された部分では綺麗な眼底が見えてきます。
白内障手術
白内障手術を同時に行う際には、単焦点眼内レンズまたは多焦点眼内レンズを選択します。従来は黄斑前膜などの黄斑疾患がある場合には、単焦点眼内レンズを選択するのが一般的でしたが、眼内の状況によっては多焦点眼内レンズを使用することが可能です。
黄斑前膜の手術を行う際の白内障手術において、多焦点眼内レンズの使用を希望される場合には、『黄斑前膜の硝子体手術と多焦点眼内レンズ』をご覧ください。一般的な白内障手術については、以下のページで詳しく説明しています。
黄斑前膜の手術費用
また、白内障手術を同時に行う場合にも費用の負担が変わります。
片眼あたりの費用の概算は下記のとおりで、金額には手術費用とその他にかかる費用を含んでいます。
| 69歳以下 | ||
|---|---|---|
| 年収目安 | 負担割合 | 手術費用 |
| 1160万円~ <区分ア> |
3割 | 約120,000円 (約150,000円*1) |
| 770~1160万円 <区分イ> |
||
| 370~770万円 <区分ウ> |
上限80,100円 | |
| ~370万円 <区分エ> |
上限57,600円 | |
| 住民税非課税 <区分オ> |
上限35,400円 | |
| 70~74歳 | ||
| 区分 | 負担割合 | 手術費用 |
| 現役並みII / III | 3割 | 約120,000円 (約150,000円*1) |
| 現役並みI | 上限80,100円 | |
| 一般 | 2割 | 上限18,000円 |
| 住民税非課税 <区分I / II> |
上限8,000円 | |
| 75歳以上 | ||
| 区分 | 負担割合 | 手術費用 |
| 現役並みII / III | 3割 | 約120,000円 (約150,000円*1) |
| 現役並みI | 上限80,100円 | |
| 一定以上の所得 <一般II> |
2割 | 上限18,000円 |
| 一般所得 <一般I> |
1割 | |
| 住民税非課税 <区分I / II> |
1割 | 上限8,000円 |
| *1: 白内障手術を同時に行った場合 | ||
上記の表で上限と記載されている金額は、高額療養費制度による自己負担限度額に達する場合となります。
よくある質問
ゆがんで見える症状は元に戻りますか?
黄斑前膜により生じたゆがんで見える症状(変視症)は、手術を行っても完全に戻ることはほとんどありません。また、黄斑前膜がない方の目に比べて物の大きさが大きく見える(大視症)の症状についても同様です。
矯正視力が良好な場合には手術を勧められず経過観察になることも多いですが、変視症や大視症の自覚がある場合には当院までご相談ください。
黄斑前膜がある場合に、多焦点眼内レンズは選択できますか?
眼内の状況によっては、多焦点眼内レンズを選択することが可能です。ただし、回折型多焦点眼内レンズを選択することはできず、焦点深度拡張型(EDOF)多焦点眼内レンズであれば使用することができます。
黄斑前膜の手術(硝子体手術)と白内障手術を同時に行う場合の眼内レンズ選択の詳細については、以下をご覧ください。
黄斑前膜が自然に剥がれることはありますか?
黄斑前膜が自然に剥がれて治ることはありません。治療せずに経過観察にした場合には、徐々に網膜の形態は悪化し、視力の低下や変視症の程度は進行します。症状の進行速度は人によって様々であるため、定期検査により黄斑前膜の程度を確認しておくことが大切です。
黄斑前膜が再発することはありますか?
黄斑前膜は再発することがあります。初回手術で黄斑前膜を適切に除去することができていても、一定の確率で黄斑前膜は再発します。
黄斑前膜を除去する際に、網膜の最表層にある内境界膜という組織も除去することで、再発の確率を下げることができます。しかし、内境界膜を除去すると緑内障が進行することがあり、緑内障を合併している方では慎重に治療方針を検討する必要があります。
術後はどのぐらいで視力が回復しますか?
記事監修者について

日本眼科学会認定 眼科専門医
東京科学大学眼科 非常勤講師
大学病院や基幹病院において多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京科学大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。