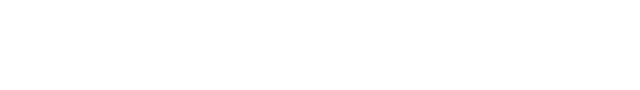硝子体出血
硝子体出血とは
硝子体出血とは、目の奥の硝子体に出血が起こった状態です。本来は透明なゼリー状の組織である硝子体に出血が生じているため、急激な視力の低下を自覚します。様々な原因によって眼内に出血が起こり、病態によっては緊急の治療が必要となることもあるため注意が必要です。
硝子体出血の検査
硝子体出血が少量であれば眼底検査で、目の奥の状態を確認することができます。しかし、出血量が多い場合には通常の眼底検査で目の奥の状態を確認することが困難であるため、超音波(エコー)検査装置を用いて診察を行います。
下の写真は糖尿病網膜症の方の眼底写真で、左眼は綺麗な眼底で血管構造などを明瞭に確認できますが、右眼は硝子体出血により眼底の状態を全く確認することができません。このような状態の場合に、超音波検査で精査を行います。
硝子体出血を起こす病気
硝子体出血を起こす病気には、以下があります。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症が重症化し、網膜に異常な血管(新生血管)が形成され、新生血管が破綻することで眼内に出血を生じます。糖尿病網膜症はいくつかのステージに分けられますが、新生血管が形成されるまで進行した状態を増殖糖尿病網膜症といいます。
硝子体出血自体は1ヶ月程度で自然に消失することもありますが、出血が自然に改善しない場合には硝子体手術が必要となります。また、更なる新生血管が生じるのを予防するために、眼底へのレーザー治療も必要です。
増殖糖尿病網膜症は進行すると、増殖膜(異常な増殖した線維組織)による牽引性の網膜剥離を合併することがあります。牽引性の網膜剥離は難治性で、硝子体手術を行う際には、可能な限り増殖膜を切除した上で、剥がれた網膜を接着させるように治療を行います。網膜を十分に接着させるために、眼内に医療用のガスやシリコンオイルを充填する場合があります。
網膜剥離
網膜剥離は、網膜の一部に穴(網膜裂孔)が空き、網膜裂孔に液化した硝子体が流れ込むことで網膜が剥がれる病気です。網膜に穴があく際に、網膜の血管が損傷されると硝子体出血を生じます。
網膜剥離は治療が遅れると視機能の予後が悪くなるために、緊急の治療が必要となります。
網膜細動脈瘤破裂
網膜の動脈に形成された血管瘤(けっかんりゅう)が破裂することで、眼内に出血(硝子体出血)を引き起こします。高血圧の人に生じやすいです。
硝子体手術により硝子体出血の除去を行います。未破裂の動脈瘤を発見した場合には、将来的に破裂して出血することを防ぐために、レーザー治療で動脈瘤を焼き固めることもあります。
加齢黄斑変性
網膜の中心部分(黄斑)に異常な血管(新生血管)が形成され、網膜内に出血や浮腫を生じる病気です。黄斑の構造が乱れることで、視力低下やゆがんで見える症状(変視症)を来すことが一般的です。
新生血管からの出血は通常は網膜内に留まりますが、まれに硝子体にまで出血が及ぶことがあり、急激な視力低下を引き起こします。硝子体出血を生じた場合には、硝子体手術によって出血を除去します。加齢黄斑変性は新生血管の性状によりいくつかの病型に分類されますが、特にポリープ状脈絡膜血管症(PCV)と呼ばれるものは、ポリープ状病巣の破裂によって多量の出血を生じることがあります。
網膜静脈閉塞症
網膜の静脈が閉塞し血流不足となった網膜に異常な血管(新生血管)が生えてきて、その新生血管が破綻して眼内に出血した状態です。硝子体出血自体は1ヶ月程度で自然に消退することもありますが、出血が自然に改善しない場合には硝子体手術が必要となります。また、更なる新生血管が生じないようにするために、血流不足(虚血状態)の網膜に対してレーザー治療を行います。
上記の写真では右眼に古い網膜静脈閉塞症があり、新生血管が破綻したことで生じた硝子体出血を眼底下方に認めます。左眼の写真は出血などは生じていませんが、動脈の壁が白くみえる変化(黄色矢印)や硬くなった動脈が静脈を押しつぶしている(青矢印)などの所見があり、もともと血圧が非常に高かったことがわかります。高血圧網膜症についてはこちらをご覧ください。
Terson症候群
Terson症候群(テルソン症候群)は、くも膜下出血や脳内出血の後に、眼内にも出血を生じた状態です。発症機序は明らかになっていないものの、脳出血によって頭蓋内(頭蓋骨に囲まれた脳が占める領域)の圧が高くなると、網膜の静脈の流れが悪くなって出血すると考えられています。両眼性に出血が生じることもあり、くも膜下出血の治療後に全身状態がよくなったのに、見え方が悪そうな様子に周りの方が気づいて病気が発見されることがあります。
外傷
目に鈍的な外傷が加わると、網膜血管の一部が破れることで眼内に出血を生じます。目にボールやこぶしが当たるなど原因は様々です。外傷で硝子体出血を起こした場合には、外傷性の網膜裂孔を原因とした網膜剥離が隠れている可能性があるため十分な注意が必要です。
上記左側の写真では多量の出血が硝子体に舞っているのがわかります。右側の写真は同一の目の異なる部位ですが、網膜に境界明瞭な白色の領域が生じており網膜振盪と呼ばれます。網膜振盪は強い外傷のエネルギーのより、網膜外層が障害を受けることで生じると考えられています。
硝子体出血に対する硝子体手術
下記は糖尿病網膜症が原因で硝子体出血となった方に対して、硝子体手術を行なっている際の術中写真です。
①では眼の中心に赤い出血がありますが、出血を硝子体カッターにより除去すると、②のように綺麗な眼底が見えてきます。今後の硝子体出血の再発予防のために、眼底の中心部を除いた周辺部全体にレーザーを照射を行うと、③のようにレーザー照射を行なった部分が白い多数の斑点として確認できます。
眼内の状況にもよりますが、当院では単純な硝子体出血に対する手術の所要時間は10分程度です。眼内に増殖膜や網膜剥離など別の病態があれば、手術時間は長くなります。病気が進行していると1-2時間かかる場合もあり、病態の複雑さによって手術の難易度は千差万別と言えます。進行しきってしまい、一般的に治癒が見込めない状態であっても当院では治療可能な場合があるので、他院で治療を断られた患者様におかれましてもご相談ください。
手術費用
硝子体出血に対する硝子体手術は保険適用となるため、患者様の年齢や収入によって費用の負担が変わります。硝子体出血は、出血を起こした原因によっては手術の内容が変わるため、それに伴って手術費用が変動します。また、白内障手術を同時に行う場合にも費用の負担が変わります。
片眼あたりの費用の概算は下記のとおりで、金額には手術費用とその他にかかる費用を含んでいます。
上記の表で上限と記載されている金額は、高額療養費制度による自己負担限度額に達する場合となります。
高額療養費制度とは、医療費の負担が高額になった場合に1か月あたりの医療費の支払い金額の上限を定めている制度で、限度額を上回った金額が払い戻しされます。高額療養費制度の詳細については下記をご参照ください。
記事監修者について

眼科医 渡辺 貴士
日本眼科学会認定 眼科専門医
東京科学大学眼科 非常勤講師
大学病院や基幹病院において多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京科学大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。