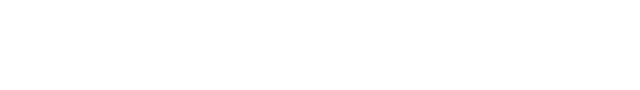強度近視(病的近視)
強度近視・病的近視とは
一般的な近視であれば、眼鏡やコンタクトレンズの装用により視力は保たれます。しかし、強度近視の進行により眼軸長が長くなると、眼球の後方の組織(網膜や視神経)が引き伸ばされることで様々な病気を生じ、視機能が低下します。この状態を病的近視と呼びます。
強度近視の合併症
強度近視に伴う眼の合併症については以下のものがあります。
網膜が引き伸ばされて網膜が裂けた状態です。
網膜内に異常な血管(新生血管)が侵入して、黄斑部に出血を生じた状態です。
視神経や視神経線維が引き伸ばされた状態です。
網膜や脈絡膜が著しく菲薄化することで、網膜や脈絡膜が萎縮した状態です。
近視性牽引黄斑症
網膜分離の初期段階では自覚症状はほとんどありませんが、網膜分離が進行するにつれて、視力は徐々に低下します。
最終的に網膜剥離(網膜が剥がれた状態)や黄斑円孔(網膜の中心部に穴があいた状態)などの重篤な状態に至ると視力は著しく低下し、治療を行っても視機能の回復は限定的になります。
上図は網膜の断面図を見る検査(OCT)ですが、近視性牽引黄斑症が①→②→③のような形で進んでいきます。
①では、黄斑周辺部で網膜分離を認めますが、黄斑中心部の構造は保たれています。②では、網膜分離が進行して網膜分離の丈が高くなっている上に、部分的に網膜剥離の所見も認めます。③では、さらに網膜の中心部に穴があく黄斑円孔を合併しています。③の状態を黄斑円孔網膜剥離といい、手術は非常に難しく、手術が無事に終わっても視力の回復は限定的になります。
近視性脈絡膜新生血管
近視性脈絡膜新生血管は、活動期、瘢痕期、萎縮期の3つの段階で進行します。このうち治療の対象になるのは活動期の近視性脈絡膜新生血管です。活動期には前述の出血がみられたり、滲出性変化といって網膜が浮腫を起こしたり、病勢が強い場合には網膜剥離を生じる場合もあります。
治療は、抗VEGF薬と呼ばれる薬を眼内に注射します。抗VEGF薬の硝子体内注射により、新生血管の勢いを抑えることができます。1回の注射で病態の改善が得られることが多いものの、再発を繰り返した場合には複数回の注射が必要になります。
活動期が終わった近視性脈絡膜新生血管は、瘢痕期に移行します。瘢痕期には出血や滲出性変化は見られなくなり、新生血管自体が小さい場合や、病変が黄斑から外れている場合には比較的良好な視機能が保たれることもあります。一方で、大きな病変が黄斑の中心に存在する場合や、活動期に網膜障害が強く起こった場合においては、瘢痕期においても視力低下やゆがみの症状が強く続くことがあります。
瘢痕期の新生血管は、瘢痕期のまま沈静化してしまうこともありますが、萎縮期に進行すると新生血管周囲の網膜が萎縮してしまいます。それはしばしば黄斑を含む(近視性脈絡膜新生血管関連黄斑萎縮)ため、重篤な視機能低下の原因となります。近視性脈絡膜新生血管関連黄斑萎縮は、病的近視による失明は主要な原因の一つです。このことから、近視性脈絡膜新生血管の治療(早期発見・診断、治療)は病的近視眼の視機能予後に直結すると言えます。
単純型黄斑部出血
近視性の脈絡膜新生血管と鑑別が必要な状態に、単純型黄斑部出血(Hs)があります。眼球が引き伸ばされてBruch膜に亀裂が入った時に、脈絡膜の毛細血管が障害された時に生じる出血です。急激な視力の低下を自覚しますが、異常な血管(新生血管)が生じているわけではないため、時間経過とともに自然に治癒します。
ただし長期的には網脈絡膜萎縮や新生血管の発症につながることがあるため、注意して経過をみることが必要です。
近視性視神経症
緑内障(視神経が障害されることで視野が欠ける病気)と同様に、点眼薬で眼圧を下げる治療を行います。眼圧が低下すると視神経にかかる負担が軽減し、視野が欠けていく速度を緩和することができます。
一度欠けた視野は元に戻ることはないので、強度近視の方では定期的な視野検査を行い、早い段階で治療を開始することが重要です。
近視性網脈絡膜萎縮
眼球が前後方向に引き伸ばされる際に、網膜や脈絡膜も同時に引き延ばされ、薄くなってしまいます。これに伴い網膜の裏の脈絡膜血管が透見されるようになり、この状態を豹紋状眼底(または紋理眼底)といいます。豹紋状眼底は近視性網脈絡膜萎縮の第一段階といえますが、この状態では視機能に与える影響はほとんどありません。
さらに近視性網脈絡膜萎縮が進行すると、びまん性網脈絡膜萎縮とよばれる変化が生じます。萎縮部分が黄色くみえることから「黄色い眼底」と言われる病変です。初期には点状・線状の萎縮から始まり、萎縮の進行に伴って面状に萎縮病変が拡がっていくことが知られています。
病的近視の病型を分類したMETA-PM分類によれば、びまん性網脈絡膜萎縮以上の近視性網脈絡膜萎縮を伴う症例について「病的近視」と定義しています。小児期にびまん性網脈絡膜萎縮がみられる場合、将来病的近視に進行するリスクが高いことが分かっており、視力予後を予測する上でも非常に重要な病変です。近年では、病的近視による失明リスクを下げるために、びまん性網脈絡膜萎縮が小児期に観察された場合には近視を進行させない取り組みが重要であると考えられています。
ついにはBruch膜という網膜のすぐ下にある膜に孔が開いてしまい、その後孔が癒合、拡大することで進行していく限局性網脈絡膜萎縮に至ります。限局性網脈絡膜萎縮が生じた網膜に対応する視野は絶対暗点(視野の欠損)となりますが、中心を脅かすことは極めて稀で、これが進行したとしても中心視力障害の原因になることはほとんどありません。中心視野を障害し、著しい視力低下の原因になる網脈絡膜萎縮としては、前述の近視性脈絡膜新生血管関連黄斑萎縮が知られており、一度生じると視機能予後は不良です。
Bruch膜の病変としては、Bruch膜の亀裂のような病変であるLacquer crack (Lc)があり、これが将来的に限局性網脈絡膜萎縮に進行することがあることも報告されており、病的近視において様々な病態に関与すると考えられています。META-PM分類においても、近視性脈絡膜新生血管やFuchs斑とならぶプラス病変として分類される、非常に重要な所見です。
よくある質問
強度近視の進行を抑制できる方法はありますか?
近視の進行は眼軸長の伸展によるものであり、既に強度近視に至っている場合には進行を抑制する有効な治療法はありません。しかし、白内障手術を行うことで近視の程度を軽くすることができ、年齢によっては白内障手術により快適な見え方を実現できることがあります。
子供の近視進行を抑制する方法はありますか?
小児期にオルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼による治療を行うことで、近視の進行を抑制できることがわかってきました。完全に進行を止めることはできないものの、少しでも近視の程度を軽減することができれば、将来の強度近視に伴う合併症を予防することにもつながります。
記事監修者について

日本眼科学会認定 眼科専門医
東京科学大学眼科 非常勤講師
大学病院や基幹病院において多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京科学大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。