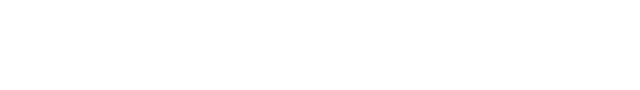オルソケラトロジー適応検査
オルソケラトロジー治療が可能かを判断するためには、適応検査が必要です。このページでは当院で行っている適応検査の流れについてご紹介します。
STEP 1:目の状態を確認する検査
以下の検査を行って、目の状態を確認します。
・屈折検査:近視の度数(度数の強さ)を確認します。
・視力検査:屈折検査の値を参考にして、裸眼視力や矯正視力を測定します。
・角膜内皮細胞検査:角膜を透明に保つために必要な角膜内皮細胞の数を測定します。
・角膜形状解析検査:角膜の形状や乱視の程度を詳しく調べます。
・眼軸長検査:眼軸長(眼の前後の長さ)は近視が強くなるほど長くなるため、眼軸長は近視進行の程度を確認するために重要な指標となります。
STEP 2:治療の適応判定
各種検査の結果は以下のような基準をもとに、治療の可否を判断します。
仮性近視と軸性近視
近視には仮性近視と軸性近視があり、一般的に「近視」と呼ばれる場合は軸性近視のことをさしていることが多いです。軸性近視は眼軸長が伸長した状態で、一度伸びた眼軸長は元に戻らないため近視治療の適応となります。一方で、仮性近視は目の調節力が過剰に働いた結果生じる一時的な近視の状態であり、過剰な調節力を取り除くことで視力が改善するため、近視治療の適応にはなりません。
角膜乱視
角膜乱視には直乱視、斜乱視、倒乱視があります。直乱視は若い方の乱視として頻度が高いもので、直乱視の場合にはオルソケラトロジー治療を行うこと可能ですが、斜乱視や倒乱視の場合は治療適応外になります。直乱視であっても乱視の度数が強い場合には、通常のレンズでは対応できず特殊レンズで治療を行うことがあります。
角膜内皮細胞
角膜内皮細胞は角膜を透明に保つために必要な細胞で、加齢やコンタクトレンズの長期使用で減少し、一度減少した細胞は回復することはありません。角膜内皮細胞が著しく減少すると水疱性角膜症を発症し、角膜に難治性の混濁を生じて視力が低下します。治療前の段階で角膜内皮細胞数が少ない場合には治療を行うことができません。
治療適応がある場合
各種検査の結果が問題なく治療の適応があれば、次の段階であるレンズのフィッティング確認へ進みます。近視度数や角膜形状などを考慮して、最適なトライアルレンズを決定します。
治療適応外である場合
オルソケラトロジーが適応外であった場合の選択肢としては、低濃度アトロピン点眼を用いた近視治療があります。オルソケラトロジーとは異なり裸眼の視力を改善することはできませんが、低濃度アトロピン点眼(リジュセアミニ点眼液)を1日1回点眼することで、近視進行を抑制することができます。
STEP 3:フィッティング確認
視能訓練士のサポートのもと、トライアルレンズを用いて、実際にオルソケラトロジーを院内で装用します。お子さま自身または保護者の方と一緒に問題なくレンズの装用を行うことができるか、レンズのフィッティングは問題ないかなどを確認します。最初のトライアルレンズでフィッティングが不適切である場合には、レンズの形状を変更してフィッティングが適切な状態になるようにレンズの調整を行います。
STEP 4:トライアルレンズの装用
トライアルレンズを1時間程度装用した後、レンズを外した上で再度視力検査を行います。短時間の装用でも角膜の形状が変化するため、この時点でも裸眼視力の改善を自覚できる場合があります。トライアルレンズ装用中は、院内で安静にお過ごしいただきます。
STEP 5:治療開始
医師より治療内容や注意点について改めて説明を聞いた上で、治療を希望される場合には治療開始となります。
治療の初期費用をお支払いいただいた段階で、治療用のレンズを注文します。注文から3営業日以降で当院に到着するので、ご都合のよい日に受け取りにお越しいただきます。レンズをお渡しする際に、レンズケア用品一式(レンズの洗浄保存液、レンズ保管用ケース、レンズ装着液など)もお渡しします。
レンズ装用を開始した、2週間後、1ヶ月後、3ヶ月後に定期検診にお越しいただきます。問題がなければ、以降は3か月ごとの定期検査を行います。
適応検査の費用
よくある質問
レンズをつけるのは痛くないですか?
初めてオルソケラトロジーレンズを装用する際にはある程度の不快感を伴いますが、強い痛みを生じることはまれで、異物感やごろごろ感は装用を続けるうちに慣れて気にならなくなることが多いです。また、初回装用時の不快感は、オルソケラトロジー装用が可能かどうかを判断する材料にもなります。
適応検査中に外出することは可能ですか?
オルソケラトロジーレンズは就寝中に装用するレンズであり、トライアルレンズのフィッティングを確認している間はできるだけ同じ状況になるように、安静に院内でお過ごしいただく必要があります。
適応検査はどのくらい時間がかかりますか?
各種検査、フィッティングの確認、診察、装用練習などで、合計約90分程度の時間を要します。お時間に余裕をもってご来院ください。
記事監修者について

日本眼科学会認定 眼科専門医
東京科学大学眼科 非常勤講師
大学病院や基幹病院において多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京科学大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。