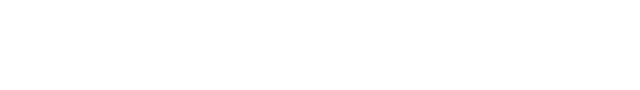ドライアイ
ドライアイとは
ドライアイとは、眼の表面をうるおしている涙液量の不足や涙液層が不安定になることで、眼の渇きや眼の違和感(ゴロゴロする、ヒリヒリする)などを生じる病気です。涙液が不足した状態では眼表面が傷つきやすく、傷の程度が強くなると視力低下も自覚するようになります。
ドライアイの原因は様々ですが、パソコンやテレビなどを長時間見るような生活では、まばたきの回数が減り涙が蒸発しやすくなるためドライアイを生じやすくなります。また、コンタクトレンズの長時間の装用も眼表面の涙のバランスを損なうためドライアイになりやすいです。
ドライアイの診断
通常の観察方法では涙液の量や分布などの精密な評価を行うことは難しいため、眼の表面に特殊な薬(フルオレセイン)をつけて涙液を可視化して診察を行います。
眼を開けた後どのぐらいの時間で、眼表面を潤していた涙液が干上がるか(涙液層破壊時間:break up time)を計測します。また、眼表面の傷もフルオレセインの染色により明瞭に確認することができます。
ドライアイ研究会により示された診断基準では、①眼の不快感や見え方の違和感などの自覚症状があること、②涙液層破壊時間(break up time:BUT)が5秒以下であることの2点を満たした状態がドライアイとされています。
左側の写真では、眼を開いた直後に涙液が乾いた領域が出現しており、典型的なドライアイの所見です。右側は重症なドライアイの方の写真ですが、眼表面に多数の傷がついていることがわかります。
ドライアイの治療
点眼治療
ドライアイ治療の基本は点眼薬です。点眼薬には「ヒアレイン点眼液®︎、ジクアス点眼液®︎、ムコスタ点眼液®︎」などの複数の処方薬があるため、患者様の症状に応じて使い分けます。
また、薬局で購入できる点眼薬の中では、涙液の成分に近い性質を持つソフトサンティア®︎がよく使用されます。
涙点プラグ
点眼薬による治療だけでドライアイ症状が改善しない場合には、涙点プラグという治療方法を検討します。
涙は、涙腺で産生されて眼表面を潤した後、涙点(上涙点・下涙点)に流れこみ、最終的には鼻の方に流れていきます。点眼薬を使用した後に喉の奥に苦味を感じることがあるのは、このように涙が最終的に喉の方まで流れていく経路があるためです。
涙点プラグは、眼表面から涙が流出する部位である涙点をふさぐことで、涙の流出量を減らして眼表面をうるおすことを目的としています。
涙点プラグには、①シリコーン製の涙点プラグと、②アテロコラーゲン製の涙点プラグの2種類があります。
シリコーン製涙点プラグ
シリコーン製の涙点プラグは、長期にわたって涙点を閉鎖できる点が優れています。しかし、涙点プラグが眼表面に接するために異物感を生じる場合や、プラグが脱落したり涙道内に迷入したりする可能性があります。
アテロコラーゲン製涙点プラグ
アテロコラーゲンとは、コラーゲンを医療用に安全に使用できるようにしたものです。アテロコラーゲンを涙小管内に詰めることによって、涙の流出を防ぎます。有害事象が特にない点が優れていますが、涙小管内に詰めたアテロコラーゲンは徐々に流れ消失するため、繰り返しの治療が必要になる点がデメリットです。
当院ではキープティア®︎と呼ばれる製品を使用して治療を行っています。
マイボーム腺機能不全
ドライアイの原因の1つにマイボーム腺機能不全(MGD)という状態があります。まぶたの縁(眼瞼縁)には、眼表面の涙液が乾かないように油分(脂質)を分泌している組織(マイボーム腺)があります。このマイボーム腺からの油分の分泌が悪くなると、涙液が蒸発しやすくなりドライアイの状態にいたります。
また、油分が詰まったマイボーム腺内においては細菌感染が生じやすく、眼瞼縁に炎症を生じたマイボーム線炎ではまぶたの縁の違和感や不快感を感じることがあります。
上の写真では、マイボーム腺の出口部分において油分が詰まって白く固まっているのが分かります。また、マイボーム腺開口部付近の瞼縁は炎症を起こして充血している所見も認められます。
マイボーム腺梗塞
マイボーム腺機能不全に関連した病態としてマイボーム腺梗塞があります。マイボーム腺の導管内に透明または黄白色の固形物が形成された状態です。マイボーム腺の分泌物である脂質が固形化することや、脱落した導管の上皮が脂質と濃縮することにより生じると考えられています。
通常は無症状ですが、以下の症例では異物感を生じていることから、局所麻酔下で切開摘出を行いました。右側が術後2日目の写真ですが、透明と黄白色のマイボーム線梗塞が取り除かれているのが分かります。
記事監修者について

日本眼科学会認定 眼科専門医
東京科学大学眼科 非常勤講師
大学病院や基幹病院において多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京科学大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。