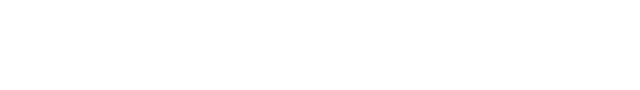目が痛い
目が痛くなる原因の多くは、目の表面である角膜や結膜に傷が付いたり、異物が付着することによって生じます。目の表面には三叉神経と呼ばれる目の知覚を担当する神経が分布しており非常に繊細なため、小さな傷であっても強い痛みを感じることがあります。
目の奥の方が痛くなった場合には、急性緑内障発作、ぶどう膜炎、視神経炎などの病態が考えられ、それぞれに適切な治療が必要となります。
<眼の表面が痛い場合>
角膜の部分に、細菌やウイルスの感染が起こり炎症を起こした状態です。痛みに加えて充血などを伴います。原因となる細菌やウイルスに対して、適切な抗菌薬や抗ウイルス薬を投与することにより治療を行います。
角膜異物、結膜異物
目の表面に砂やまつ毛などの異物が入ってしまった状態です。まずは異物が目に入ってしまった時点で、水道水で眼の表面を洗って頂くことが重要になります。眼科では、取り残されてしまっている異物がないかや、眼の表面に傷がついていないかなどを確認して、必要に応じて処置を追加します。
化学薬品が入った場合には、その薬品の種類によっては緊急性が高く、なるべく早く多量の水での洗浄が必要となることがあります。また、鉄片が入ってしまった場合には角膜に食い込んだ鉄片を取り除いた上で、鉄片の周辺に形成された錆も削り取るなど、入った異物の種類によって適切な対応を行うことが重要となります。
下記の写真の症例では、上まぶたの裏側に入りこんだ異物により、角膜の上方に細かい傷がついていることが確認できます。
角膜上皮びらん
角膜は5層の構造からできていますが、一番目の表面である角膜上皮という部分が剥がれてしまった状態で、強い痛みを感じます。外傷やコンタクトレンズの付け外しなどに伴って生じます。角膜の上皮が再生してくるまで、点眼や眼軟膏による治療を行います。再発性角膜上皮びらんといって、角膜上皮の状態が不安定であるために繰り返し角膜上皮びらんを再発してしまう方もいます。
角膜潰瘍
角膜びらんよりもさらに深い層(角膜実質)まで角膜がえぐれてしまった状態です。外傷や感染症に伴って角膜中央部が深くえぐれてしまうような状態と、全身の病気の一症状として角膜の周辺部が全体的に菲薄化してしまう状態があります。原因に応じた適切な治療が必要となります。
まつ毛は通常であれば外側へ向かって生えていますが、一部のまつ毛が内側に向かって生えてしまうことで、目の表面をこすり傷付けている状態です。目の表面の傷が軽度であれば、定期的にまつ毛を抜いたり、目薬で目の表面をうるおす治療を行います。目の表面の傷が高度な場合には手術治療が必要になる場合もあります。
まぶたをめくった部分の結膜(瞼結膜)の部分において、白色〜黄白色の粒状の病変を認める疾患です。結膜結石が結膜の下に存在しており症状がない場合には治療は不要です。しかし、結膜結石が大きくなり表面に結石が露出し目の表面こすって傷つけ痛みを伴うような場合には、結石を取り除く処置が必要となります。
記事監修 眼科医 渡辺 貴士
日本眼科学会認定 眼科専門医
東京医科歯科大学眼科 非常勤講師
大学病院や数々の基幹病院において第一線で多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京医科歯科大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。