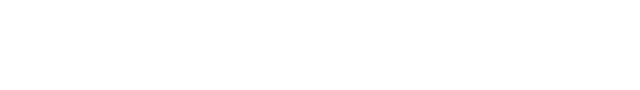網膜裂孔
網膜裂孔とは、網膜の一部に穴があいてしまった状態です。穴が空いた時に網膜の組織の一部や出血が硝子体の空間を舞うことで飛蚊症の症状が生じます。
網膜裂孔を放置したままにしておくと、網膜に空いた穴の部分から目の中の硝子体(ゼリー状の成分)の一部が液化して液体状となったものが入り込み、徐々に網膜が剥がれて網膜剥離に至ります(症例①の写真)。
網膜剥離は急速な視力低下を生じるため緊急での手術が必要となり、手術を行っても視力予後が悪くなる可能性があるため、網膜裂孔から網膜剥離への進展を防ぐためにレーザー治療が必要となります。特に飛蚊症の症状を伴う網膜裂孔は網膜剥離に進展しやすいために十分に注意が必要です。
網膜裂孔の周囲にレーザー照射を行うと、網膜の一部が焼き固められて網膜が剥がれにくい状態となります(症例②の写真)。
レーザー手術機器
従来は網膜のレーザー治療に用いるカラーレーザーと、後発白内障のレーザー治療に用いるYAGレーザーは別々の機器として独立していました。当院では、この2つのレーザーが一体化したZEISS社の「VISULAS YAGⅢ Combi」という最新の機器を導入しております。
記事監修 眼科医 渡辺 貴士
日本眼科学会認定 眼科専門医
東京医科歯科大学眼科 非常勤講師
大学病院や数々の基幹病院において第一線で多数の手術を行ってきました。特に白内障手術と網膜硝子体手術を得意としています。現在も東京医科歯科大学の非常勤講師を兼任しており、大学病院での手術指導および執刀を続けています。